生成AIの進化は企業の競争力を左右する重要な要素となっており、NTTデータは2023年に「Global Generative AI LAB」を設立し、国内外のビジネス現場に生成AIを導入するための実証と仕組み作りを加速しています。本記事では、その背景や具体的な事例、今後の展望を詳しく解説します。
NTTデータが生成AIの活用を推進するGlobal Generative AI LABを設立
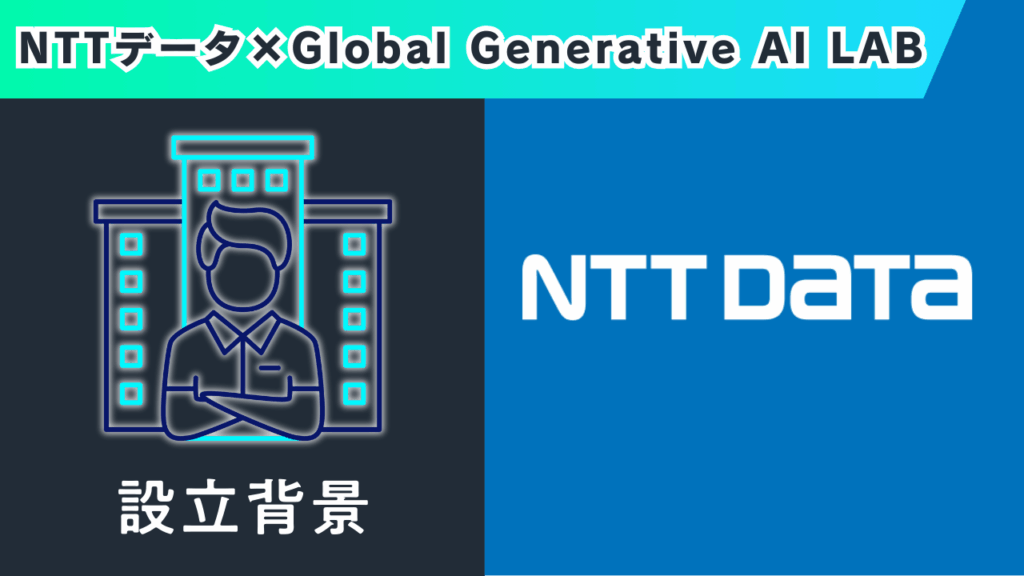
出典:NTT DATA
NTTデータは2023年、生成AIの実用化を強く推進するため「Global Generative AI LAB」を立ち上げました。ここでは、Global Generative AI LABの設立背景とその目的を解説します。
設立の背景と目的
NTTデータは2023年、生成AIの実用化を強力に推進するため「Global Generative AI LAB」を立ち上げました。この拠点は単に研究を行うのではなく、実際のビジネス課題を対象にAIを試験導入し、検証を繰り返すことで実効性を高めていく場として機能しています。
目的は明確で、国内外の企業が生成AIを安心して導入できるようにすることです。そのため、技術的な開発と同時に利用ガイドラインやリスク対応の仕組みを整備し、企業が持つ不安や疑問を解消する役割を担っています。
世界的な視野を持つ拠点として
LABの特徴は「Global」という名称が示す通り、国内にとどまらず世界各国の事例を吸収し、活用できる点にあります。欧米を中心に急速に進む生成AIの応用を調査・研究し、日本企業の実情に合わせて翻訳するように導入支援を進めているのです。
NTTデータがこれまで培ってきたグローバルネットワークを生かし、現地の企業や研究機関と情報交換を行いながら、日本の産業に役立つ形で実装していく。こうした国際的な視野を持つ拠点は国内でも希少であり、NTTデータの強みを際立たせています。
生成AIの可能性とビジネスにおける課題

ここでは、ビジネスにおける生成AIの可能性と課題をまとめました。
生成AIがもたらす価値
生成AIは、従来の情報検索や自動化を超える付加価値を生み出しています。営業現場では顧客ごとの提案資料を短時間で生成し、開発現場ではコード作成を補助することで効率化を実現。マーケティング部門では膨大なデータを整理し、最適な施策を提案できるようになりました。これらの活用は単なる効率向上にとどまらず、従業員の創造性を引き出し、より戦略的な仕事へとシフトさせる効果を持ちます。その結果、企業の競争力全体が底上げされるのです。
企業が直面するAI導入の懸念点
一方で、生成AIの導入には多くの課題も存在します。代表的なものは「誤情報(ハルシネーション)」と呼ばれる現象で、AIが根拠のない回答を自信ありげに出す場合があります。また、学習データの偏りによって公平性を欠いた結果を導くリスクも無視できません。さらに、利用者が入力した情報が外部に流出する恐れや著作権の問題も議論されています。企業はこれらを軽視すれば大きな損失を被る可能性があるため、導入と同時にセキュリティやガバナンス体制を強化し、従業員への教育を徹底する必要があるのです。
Global Generative AI LAB 導入事例まとめ

ここでは、Global Generative AI LABの導入事例を5つまとめました。
ソフトウェアマイグレーションの商用適用
NTTデータは、レガシーシステムからの移行(マイグレーション)に生成AIを活用する取り組みを進めています。特に日本とスペインの拠点では共同でPoCを行い、製造工程の約70%を合理化し、生産性を約3倍向上させた商用事例が公表されました。2023年10月以降は国内でも複数のPoCを展開し、マイグレーションの効率化を本格的に進めています。
Dolffia(文章検索AI)のPoC(技術検証)
Global Generative AI LABを通じて開発された「Dolffia」は、自然言語での検索やドキュメント要約を可能にするソリューションです。NTTデータ社内での運用を経て、国内顧客とのPoCを開始しました。
従来のキーワード検索に比べ、文脈を踏まえた検索が可能となり、ナレッジ活用の精度が大幅に改善。今後はNTTデータのナレッジ管理基盤「knowler」と統合される予定です。
eva(生成AIチャットボット)の国内展開
欧州拠点で展開されてきた生成AIチャットボット「eva」は、Global Generative AI LABの支援を受けて日本国内でもPoCが進められています。
定型的な問い合わせ対応を自動化するだけでなく、文脈を踏まえた自然な対話が可能となり、顧客サポートや社内ヘルプデスクの効率化が期待されています。国内の顧客企業に合わせた応答精度の検証も進行中です。
LITRON®(文書読解AI)との連携
NTTデータ独自の文書読解AI「LITRON®」は、契約書や監査資料の解析に強みを持っています。2023年6月にはGlobal Generative AI LABの活動として、LITRON®に生成AIを組み合わせた新サービスが発表されました。
これにより、単なる文書検索や要約にとどまらず、文脈を理解した高度な分析や知識抽出が可能になり、法務・監査・研究開発といった分野での業務効率化が期待されています。
自社開発・ナレッジ共有への適用
Global Generative AI LABは顧客支援だけでなく、NTTデータ自身の開発業務やナレッジ活用にも生成AIを導入しています。ソフトウェア開発の一部では生成AIによるコード生成やテスト支援を取り入れ、開発スピードの向上を確認。
また、社内の教育・Eラーニングにも活用され、AIを活かした人材育成環境を整えています。これら自社適用で得られた知見は、そのまま顧客向けソリューションに還元されています。
NTT DATAの生成AI導入事例
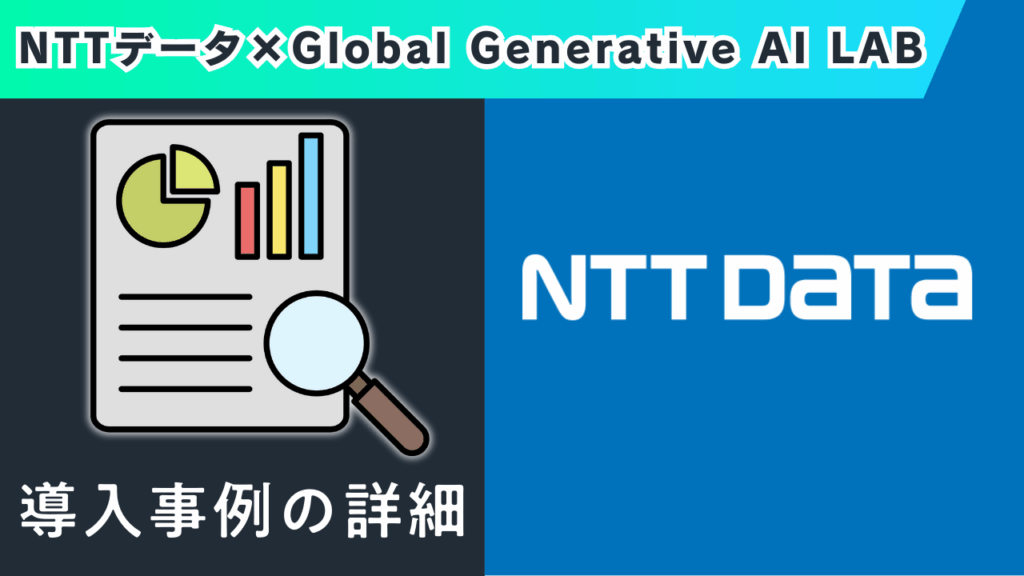
ここでは、NTTデータが取り組んだ生成AIの活用事例を4件ご紹介します。分野も利用目的も異なりますが、いずれも「実際に現場の仕事をどう変えたか」という視点で見ると、その意味がよりはっきりと浮かび上がってきます。
航空券予約システムでの「Coding by NTT DATA」活用
同社は自社で開発したコード変換アセット「Coding by NTT DATA」を、航空券予約システムのJava更新作業に使いました。Java8からJava17への移行は本来膨大な工数を要しますが、生成AIがコード変換を支援した結果、作業時間は55%削減。
確認作業自体は手作業より増えたものの、修正効率が大幅に改善されました。単純なスピードだけでなく「安心して動かせるコードを短期間で仕上げられる」という効果もあり、実務現場の生産性向上に直結した事例として注目を集めています。
官公庁向け書類分類・検索のTPU活用 PoC
公共分野でもNTTデータは生成AIを活かしています。官公庁業務における書類分類や検索を効率化するPoCで、Google CloudのTPUを利用。一般的なプロセッサでは時間がかかる学習を、約20倍ものスピードで実行でき、短期間でドメイン特化モデルを構築しました。
複雑な行政文書処理の実験環境をすばやく整備できたことは、業務改善への弾みとなり、AI導入の可能性を現場に実感させた大きな一歩だったといえます。
広告・デザイン現場のクリエイティブ支援(AWS連携)
AWSジャパンが主催する生成AIプログラムに参画し、NTTデータはAIエージェントを活用したクリエイティブ支援ソリューションを開発しました。広告制作や店頭POPのデザインといった業務は専門知識が必要でしたが、この仕組みにより、店舗スタッフのような非専門人材でも短時間で作業が可能に。
経験者にとっても、AIが発想を補うことでラフ案作成の負担が減り、作業の幅が広がりました。人材の層を問わず使える柔軟性が評価され、現場での実用性が確認されています。
メディア業界における気象ニュース原稿の自動生成(AIによる自動記事生成)
国内メディア企業との協力で、NTTデータは気象ニュース原稿を生成AIで自動作成する実証を行いました。4年分の気象電文と実際のアナウンサー原稿を学習データに用いた結果、生成された文章は自然で読みやすく、実際に人が読む際も違和感が少ないと評価されています。
意味の精度には修正が要る場合もありましたが、定型ニュースの自動生成には十分応用可能と判断されました。さらに決算情報やスポーツ記事など、扱う対象を広げた実験へと展開されています。
生成AI活用の今後の展望

今後ビジネスにおける生成AIはどのようなポジショニングを確立し、キャリアに影響を与えるのでしょうか?大きく分けて5つの影響を解説します。
意思決定の迅速化
生成AIは膨大なデータを短時間で解析し、複数のシナリオを提示できる点で経営判断に大きな価値を持ちます。従来は数日かかっていた市場調査やリスク分析を数時間で提示できるようになれば、経営層は素早く意思決定が可能になります。競合の動きが速い現代において、スピードは競争優位を左右する重要な要素です。AIを活用した意思決定プロセスは、今後ますます多くの企業に浸透していくでしょう。
人材育成とAIの共存
生成AIは人材育成のあり方にも大きな変化をもたらします。経験の浅い社員がAIを通じて知識を補うことで、成長スピードが速まるからです。特に若手人材がベテランの知見を短期間で吸収できる環境が整えば、組織全体の底上げが可能になります。ただし、そのためには社員が安心してAIを利用できる教育体制が不可欠です。人材育成とAI導入を両立させる取り組みは、今後の企業競争力を左右するテーマになるでしょう。
倫理・ガバナンスの確立
生成AIの普及が進むほど、倫理やガバナンスの問題は避けて通れません。AIが誤情報を発信した場合の責任は誰にあるのか、どのように監査するのかといった課題に答える必要があります。NTTデータのGlobal Generative AI LABでは、安全にAIを利用できる環境を整備するためのルール作りを推進しています。こうしたガバナンスが確立されてこそ、企業は安心してAIを使い、顧客も信頼を寄せるようになるのです。
産業横断のコラボレーション
生成AIは、異業種間の連携を促進する可能性を秘めています。たとえば製造業が金融業のリスク分析モデルを取り入れたり、教育分野が医療の事例データを参考にしたりと、これまで交わらなかった知見を橋渡しできるのです。LABはその調整役として機能し、業界横断的な協業を後押しします。これにより新しいサービスやビジネスモデルが生まれ、産業全体の競争力向上が期待されます。
人間の役割の再定義
生成AIの進化によって「人間の仕事が奪われるのではないか」という懸念は根強く存在します。しかし実際には、AIは作業を補完する存在であり、人間の役割はむしろ高度化します。AIが反復的な業務を担うことで、人間は創造性や判断力が求められる業務に集中できるのです。今後は「AIと共に働く力」が問われる時代となり、人間の役割は再定義されることになります。
まとめ
生成AIは単なる効率化のツールではなく、企業文化や産業構造を根底から変える可能性を秘めています。NTTデータのGlobal Generative AI LABは、その変革を推進する中心的な存在です。国内の導入事例からも分かるように、生成AIはすでに目に見える成果を生み出しています。今後は教育やガバナンス、産業横断的なコラボレーションを通じてさらに進化し、日本企業の競争力を押し上げていくでしょう。
NTT DATAとは?

引用:NTT DATA
NTTデータは、NTTグループの中核を担うシステムインテグレーターであり、世界60か国以上に拠点を持つグローバルITサービス企業です。金融、公共、製造、通信といった幅広い産業に対し、コンサルティングからシステム開発、運用保守までを一貫して提供しています。
近年はクラウド、データ活用、サイバーセキュリティに加え、AIや生成AIの実装に注力しており、2023年には「Global Generative AI LAB」を設立しました。ソフトウェア開発へのAI適用やマイグレーション効率化、ナレッジ検索ソリューション「Dolffia」、文書読解AI「LITRON®」、チャットボット「eva」といった取り組みを通じ、顧客のDXを推進。安心してAIを導入できるガバナンス整備にも取り組み、世界19万人を超える人材と共に「Trusted Global Innovator」を掲げ、企業の持続的成長を支援しています。



返信 (0 )