企業活動において「データ」は欠かせない存在になりました。かつては経験や勘で意思決定を行っていた場面も、今ではデータを活用しなければ競争を勝ち抜くことは難しくなっています。しかし、実際にデータを分析し、現場で使える形にするのは簡単ではありません。多くの企業が膨大なデータを持ちながら、有効活用できずに眠らせてしまっているのが現実です。
そうした課題に対してNECが提案するのが「dotData」です。分析の専門知識がなくてもAIがデータ処理や特徴量設計を自動で行い、すぐに使える結果を提示してくれる仕組みです。本記事では、セイコーエプソンがdotDataを導入した背景と変化を軸に、データ活用の未来像を探っていきます。
NECがデータ分析をAIで自動化するソフトを開発

引用:dotData
dotDataは、NECが2018年に米国シリコンバレーで立ち上げた子会社「dotData, Inc.」から生まれたデータ分析自動化ソフトウェアです。名前の通り、膨大なデータを「点(dot)」として捉え、それらをつなぎ合わせることで価値を見出すことを狙いとしています。これまでの分析では、データサイエンティストが仮説を立て、複雑な前処理を行い、数多くの特徴量を設計してきました。しかしこの作業は非常に時間がかかり、数カ月単位のプロジェクトになることも珍しくありませんでした。
dotDataはそのボトルネックを取り除くことが可能です。AIが自動で最適な組み合わせを見つけてくれるため、これまで専門家が頭を抱えていた領域を短期間でカバーできます。実際、従来なら数十人月かかっていた分析を、数日で実現できるケースも報告されています。しかも単に結果を出すだけでなく「なぜその予測になったのか」という説明を伴うため、現場が納得して使える点も大きな魅力です。これはデータ活用の民主化を支える仕組みと言えます。
NECとdotDataが提供した予測分析自動化技術

予測分析自動化技術とは、AIを活用して未来を見通す仕組みを誰でも使えるようにする技術です。従来は、①データ収集、②前処理、③特徴量設計、④モデル構築、⑤検証という長いプロセスが必要でした。この中でも特に時間がかかるのが特徴量設計です。例えば、売上データを分析する際には「曜日ごとの傾向」「天候による影響」「キャンペーン有無」といった新しい変数を人間が考え、何度も試す必要がありました。
dotDataでは、この作業をAIが代わりに行います。しかも人間が思いつかないような複雑な特徴量まで探索できるため、予測の精度が向上しやすいのです。さらに重要なのは、その仕組みを専門部署に閉じ込めず、営業や製造など現場の担当者が直接使えるようになることです。これにより、分析スピードは飛躍的に上がり、現場の意思決定も早まります。単なる効率化にとどまらず、業務スタイルそのものを変える技術だと言えます。
NECが国内導入を進めた背景

NECは2018年にdotDataの国内展開を本格的に開始しました。当初から「プロジェクトを素早く立ち上げられること」「現場で運用可能な仕組みであること」を重視しており、バージョンアップごとに機能を強化してきました。例えば、クラウド環境での導入や可視化機能の追加、APIによる柔軟な再学習など、実務に直結する改良が次々と施されています。特にAWS対応は、初期投資を抑えて試せる点で、多くの企業にとって大きな後押しになりました。
NECの狙いは単なるソフトウェア販売ではありません。「データを活用する文化を根付かせること」が本質的なゴールです。社内のデータを誰もが使える状態にし、現場の社員が自ら課題解決に取り組めるようにする。そうした仕組みを整えることで、単発の分析にとどまらない長期的なDX推進を実現しようとしています。
dotDataが果たす役割
dotDataは、NECが描く「誰もがデータを使える未来」を支える中核ツールです。分析の専門家が不足している状況でも、現場の社員が自ら分析できる環境を提供し、知見を即座に業務に反映できます。これは単なる効率化ではなく、現場主体で新しい価値を生み出す体制づくりにつながります。
エプソンが抱えていた課題
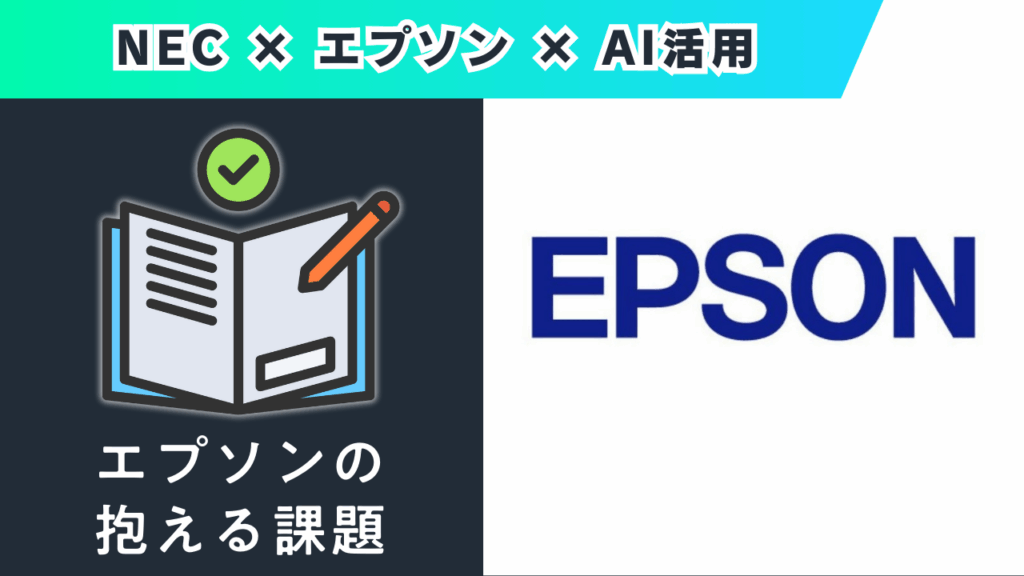
引用:EPSON
ここでは、セイコーエプソンが抱えていた課題について深掘りしていきます。
データ活用の壁
セイコーエプソンは世界規模で事業を展開する製造業ですが、社内には活用しきれていない膨大なデータが存在していました。
情報化推進部 部長の高橋一哲さんは「有効に活用できているとは言い難い状況」と語っており、データをただ蓄積するだけで終わっている現実を問題視していました。分析環境自体は整っていたものの、実際に現場で改善につながる活用には至らないケースが多かったのです。
人材不足による停滞
課題はもうひとつあります。データ分析を担える人材が限られていたことです。データサイエンティストは採用が難しく、育成にも時間がかかります。
そのため、現場の社員が「データを使いたい」と思っても、専門家に依頼して結果を待つしかない状況が続いていました。結果としてスピード感を欠き、ビジネスの変化に追いつけないという悪循環を生んでいたのです。
dotDataへの期待
高橋さんは「業務部門の一人ひとりがデータを扱い、現場で気づきを得られる仕組みを整えることが不可欠」とコメントしています。dotDataはまさにその解決策として期待されました。
分析を専門家に閉じ込めるのではなく、現場が自ら使える形にすること。これこそがエプソンに必要だった次の一手でした。
dotDataを導入することで生じた変化

ここでは、セイコーエプソンにdotDataを導入することで生じた変化をまとめていきます。
業務部門による自律的な分析
dotDataを導入したことで、エプソンは業務部門の社員が自らデータを分析できる環境を手にしました。これまでなら専門部署に依頼して数週間待っていた内容も、数日で答えを得られるようになったのです。例えば、製造現場では不具合の原因をスピーディに特定できるようになり、設備トラブルの再発防止に役立っています。営業現場では販売データをもとに需要を予測し、在庫や仕入れの最適化につなげています。社員が自分の判断でデータを扱えるようになったことは、企業文化に大きな変化をもたらしました。
バリューチェーン全体での活用
dotDataの効果は一部門にとどまりません。設計、製造、販売というバリューチェーン全体で活用が広がっています。設計段階では、過去の不具合や試験データを分析し、品質改善に直結する知見が得られています。製造工程ではセンサー情報を使った予防保全が進み、稼働停止のリスクを減らしています。販売部門では、顧客データをもとに購入傾向を予測し、在庫切れや過剰在庫を防ぐ取り組みが実現しました。このように、dotDataは企業の隅々に浸透し、全体最適化を後押ししているのです。
分析文化の定着
もうひとつの変化は、社員の意識の変化です。以前は「データ分析は専門家の仕事」という認識が強くありました。しかしdotDataの導入後、現場の社員が自ら分析を行い、成果を実感することで「データを使うのが当たり前」という文化が根づき始めています。これはDXを進める上で欠かせない基盤であり、エプソンの組織力を底上げする要因となっています。
dotData導入事例のまとめ

ここでは、dotDataの導入事例をまとめました。
事例1:ソニー銀行
ソニー銀行では、顧客が住宅ローンを契約する際の与信判断にdotDataを活用しました。従来は人手で設計していたリスク予測モデルをdotDataに置き換えることで、短期間で多くの特徴量を検証でき、与信モデルの精度が向上しました。特に「返済遅延リスクの予測」において、AIが生成した特徴量が有効に働き、顧客ごとのリスク評価がよりきめ細かく行えるようになったのです。これにより、顧客にとっても公平で納得感のある審査プロセスが実現しました。
事例2:三井住友カード
三井住友カードでは、膨大なカード取引データを活用した不正利用検知にdotDataを導入しました。従来の仕組みでは検知精度に限界があり、不正利用を見逃すケースも発生していました。dotDataを導入することで、多様な変数を短期間で組み合わせて分析できるようになり、不正利用の兆候をより早期に把握できるようになりました。結果として不正被害の削減につながり、カード利用者の安心感向上にも貢献しています。
事例3:日立物流
日立物流は、輸配送の効率化に向けてdotDataを導入しました。膨大な輸送データを解析し、ルートごとの需要予測や運行計画の最適化に活用しています。従来は経験豊富な担当者の知識に依存していましたが、dotDataによる予測モデルを取り入れることで、属人的な判断からデータドリブンな運用に移行できました。これにより輸送コストの削減とサービスレベルの向上が同時に実現しています。
まとめ:今後の展望
セイコーエプソンの事例は、データ分析の在り方を大きく変える可能性を示しています。dotDataの導入によって、現場の社員が自らデータを扱い、気づきを得て業務改善に生かす流れが定着しつつあります。これは単なる効率化ではなく、企業文化を変える動きだといえます。
NECとdotDataは今後も、こうした「分析の民主化」を支援していくでしょう。製造業に限らず、流通や金融、サービス業など幅広い業界で同様のニーズが存在します。もし「データはあるのに活用できていない」と感じているなら、この事例から学べることは少なくありません。
現場で誰もがデータを活用できる環境を整えることこそ、これからの企業競争力を左右する大きな要素になるはずです。今回の事例はあくまで第一歩に過ぎません。エプソンは今後さらにdotDataを活用し、新しいビジネスモデルの創出やグローバル拠点での展開を目指しています。NECとdotDataはその取り組みを支え、分析の民主化を広げていくでしょう。製造業にとどまらず、さまざまな業界にとって参考になる事例だと言えます。



返信 (0 )