ソフトウェア開発の現場では、近年「生成AIをどう使うか」が大きなテーマになっています。単純な効率化だけでなく、エンジニアの働き方そのものを変える可能性を秘めているからです。マイクロソフト傘下のGitHubが提供する「GitHub Copilot」も、その象徴的な存在といえます。
LINEヤフーは2023年、このGitHub Copilotを本格導入しました。対象となったのは約7,000名のエンジニア。国内でも屈指の規模を誇る組織での導入は、業界全体にとっても大きなニュースでした。本記事では、導入の背景や狙い、具体的な成果、そして今後の展望について掘り下げていきます。
LINEヤフーにおけるAI導入の背景と狙い
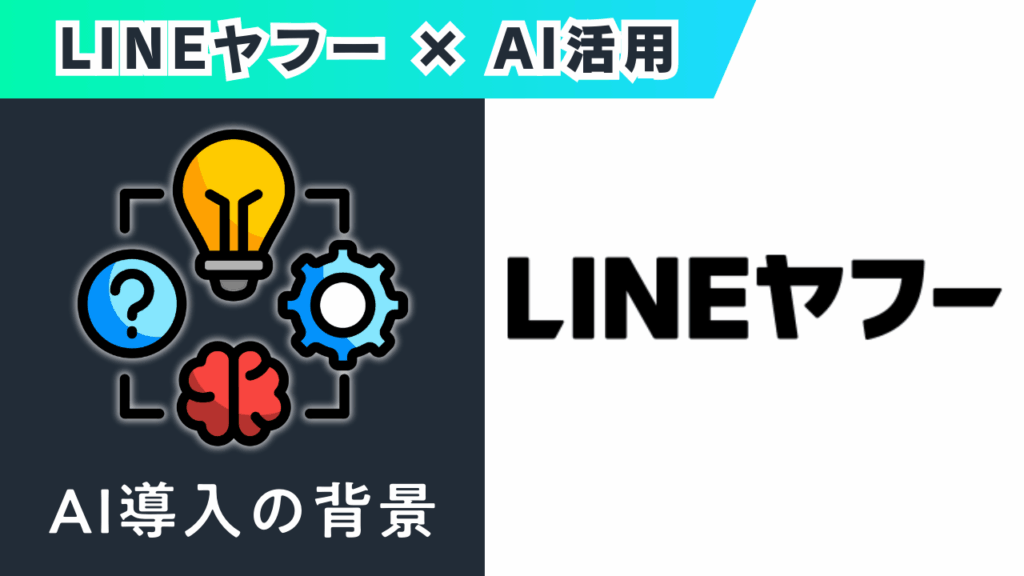
引用:LINEヤフー
ここでは、LINEヤフーが従業員2万人に生成AIを提供した背景と目的について深掘りしていきます。
コードのクオリティを均一化するためにAIを導入
LINEヤフーには約7,000名ものエンジニアが在籍しています。メッセンジャーやEC、広告、検索など幅広いサービスを支える膨大なコードを日々更新し続けており、その規模は国内でも最大級です。
その環境では「似たようなコードを繰り返し書く」「品質を均一に保つのが難しい」といった課題が常にありました。
そこで、エンジニアのコーディングをサポートするAI「GitHub Copilot」の導入を決断したのです。
GitHub Copilotとは何か
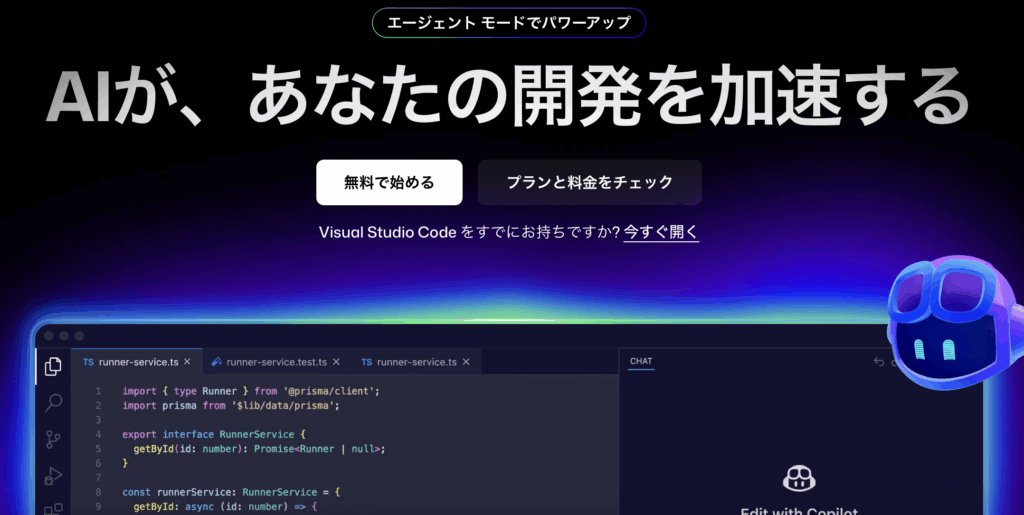
GitHub Copilotは、マイクロソフト傘下のGitHubとOpenAIが共同開発した「AIペアプログラマー」です。名前のとおり、飛行機の副操縦士のようにエンジニアを横でサポートしてくれる存在だと考えるとわかりやすいです。コードを書いているときに次の一文を提案してくれるだけでなく、関数全体やテストコードまで示すこともあります。
従来の単純な補完機能は、単語や構文の一部を埋めるにすぎませんでした。Copilotは状況を理解したうえで提案を行うため、自然に「続きを書いてくれる」ような体験になります。
例えば開発者が「ユーザー認証用の関数」を書き始めると、入力チェックからエラー処理までを自動的に提案してくれることがあります。ゼロから考えるよりも速く、しかも一定の品質が担保されるため、エンジニアは設計や高度な判断に集中できるようになるのです。
AIによってエンジニアに余裕が生まれはじめた
GitHub Copilotを導入する狙いは、単なる効率化にとどまりません。プレスリリースでは、エンジニア一人あたり1日1〜2時間の削減効果があると試算されていますが、それ以上に大きいのは「余裕を生み出すこと」です。
開発者が単調な作業から解放されれば、サービスの改善や新機能のアイデアに力を注げるようになります。また、社内では「AIを活用する文化」を根づかせることも大きな目的とされています。ツールをただ導入するだけではなく、エンジニアが安心して使いこなせる環境を整え、組織としての競争力を高めようとしているのです。
AIのテスト導入から正式導入への道のり
LINEヤフーは、いきなり全社展開したわけではありません。最初は小規模なチームでGitHub Copilotを試し、その効果やリスクを丁寧に検証しました。コーディング効率がどの程度向上するか、既存の開発フローに無理なく組み込めるか、といった観点です。並行して、セキュリティやコンプライアンス面の課題もチェックされました。AIが生成するコードには、外部データに由来する表現が含まれる可能性があるため、その扱い方を明確にする必要があったのです。
さらに同社は、導入にあたってエンジニア向けのEラーニングを整備しました。ツールの使い方だけでなく、「生成されたコードをどう評価すべきか」「どのようにレビューに組み込むか」といった実務上のガイドラインを用意したのです。こうした段階的な取り組みがあったからこそ、2023年にはエンジニア約7,000名を対象に正式導入へと踏み切ることができました。
AIの導入による成果と現場の変化

ここでは、AIの導入による成果と現場の変化について解説します。
AIの導入によって生産効率が10%〜30%向上
導入後、現場からは「繰り返しの作業が減った」「レビュー前のコードが整っている」という声が多く上がりました。エンジニア一人あたりで見ると、平均して1日1〜2時間のコーディング時間短縮が実現したといわれています。単純に時間が浮くだけではなく、空いたリソースを新しい挑戦に使えるようになったことが大きな変化です。
また、Copilotが提示するコードは必ずしも完成品ではありません。時には修正や調整が必要になりますが、その「たたき台」があることで議論が進みやすくなったといいます。チーム全体のコミュニケーションが活性化し、結果的に開発スピードも上がったのです。エンジニアの間には「AIと一緒に開発している感覚」が広まりつつあり、従来とは異なる働き方のスタイルが少しずつ根づいています。
生成AI推進体制とデジタルエシックス(倫理)の整備
LINEヤフーはGitHub Copilotを導入する際、単にツールを配布するだけでなく「生成AIをどう使うべきか」という指針を整えることにも力を入れました。AIが提案するコードは便利ですが、そのまま使えば必ず正しいとは限りません。著作権やセキュリティの観点でも注意が必要です。そこで同社は、AI活用のルールを社内で明文化し、全エンジニアに共有しました。
また、生成AIを「業務を補助する存在」として位置づけ、人間による確認を必須としています。これは、AIを盲目的に信頼するのではなく、人とAIが役割を分担しながら成果を出すことを重視している姿勢の表れです。加えて、倫理的な観点から「利用時に配慮すべき事例」や「リスクが想定されるケース」も整理されており、誰が使っても同じ基準で判断できる体制が作られています。こうした準備があったからこそ、大規模導入に対する社内の安心感も高まりました。
【LINEヤフー】今後の展望

GitHub Copilotの導入はゴールではなく、LINEヤフーにとっては新しいスタートラインです。現場での利用が広がるにつれて、どの業務で特に効果が出やすいのか、逆に課題が残るのはどこかといった知見が蓄積されていきます。同社はそうした知見を踏まえて、AI活用の領域をさらに拡大していくと考えられます。
例えば、今後はテストコードやドキュメント作成といった周辺業務への適用が進むでしょう。コード以外の領域でもAIを組み合わせることで、開発全体の効率化が期待できます。さらに、開発者教育やナレッジ共有の場面でも生成AIが役立つ可能性があります。経験の浅いエンジニアがCopilotを通じて学びながら成長する姿は、組織にとって大きな価値となるはずです。
LINEヤフーが描く未来は「エンジニアがAIと協働し、より創造的な開発に専念できる世界」です。GitHub Copilotの導入はその第一歩であり、今後の発展が大いに注目されます。
GitHub Copilotの導入事例まとめ
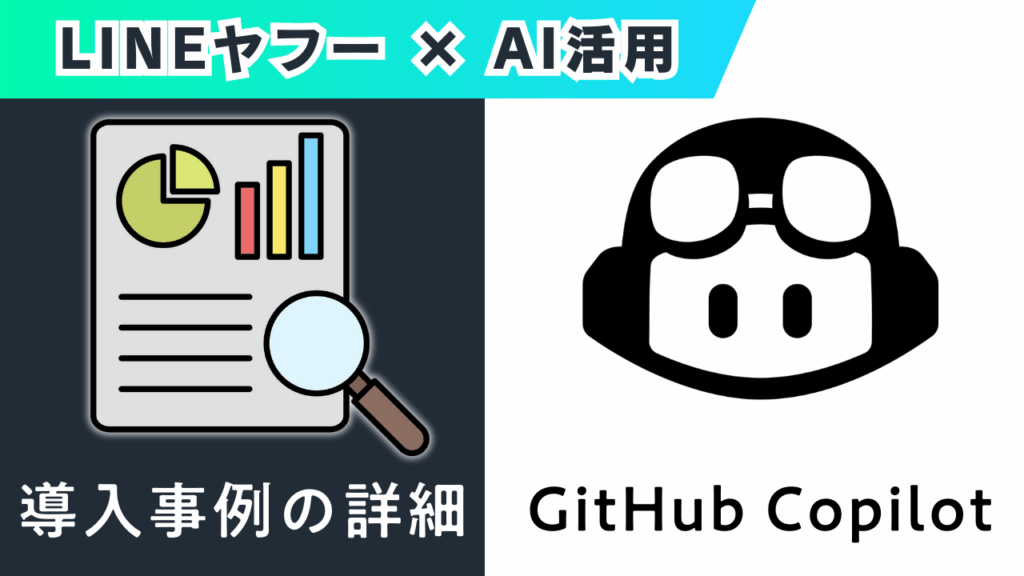
ここでは、GitHub Copilotを導入した国内企業の例をまとめました。
事例1:富士通(SI事業)
富士通は2024年7月から、システムインテグレーション事業において約2,400名のエンジニアを対象にGitHub Copilotを導入しました。背景には「レガシーコードの保守に多大な工数がかかる」「リファクタリングや障害対応に時間が奪われる」という課題がありました。
Copilotを活用した結果、Javaコードのリファクタリング業務ではAI提案により作業量が約75%削減され、可読性や保守性も向上。障害対応でもAIがエラーログ解析や修正案提示を補助し、原因特定から復旧までの流れが効率化されました。単に時間短縮にとどまらず、エンジニアが新規開発に時間を割ける環境を整える効果も確認されています。富士通は今後、利用者を2025年度末までに1万人規模へ拡大する計画を掲げており、大手SIerとして生成AIを全面的に業務に取り込む姿勢が注目されています。
事例2:サイバーエージェント
インターネット広告やメディア事業を展開するサイバーエージェントは、2023年春にGitHub Copilotを導入しました。エンジニアが膨大なコードを書き続ける環境で「AIをどう取り入れて効率化するか」という課題があり、同社は早期から実証実験を行っています。導入後の社内調査では、開発効率が約10%向上したと報告されており、繰り返し発生する定型処理やテストコード生成で大きな効果が見られました。
また、エンジニア文化として「AIをうまく活用すること」が浸透し始め、若手のオンボーディングやレビューの効率化にも寄与しています。さらに、経営陣は「エンジニアの生産性を2.5倍に高める」という長期ビジョンを掲げ、Copilotを中心に生成AI活用を戦略的に拡大しています。こうした積極的な姿勢は、国内のインターネット企業の中でも先進的な事例といえます。
事例3:NTTドコモ
NTTドコモは、通信事業を支える大規模システム開発においてGitHub Copilotを活用しています。特に数百人規模が関わるプロジェクトでは、コードの統一性や生産性の確保が課題となっていました。Copilotを導入したことで、コーディングの手間が減っただけでなく、レビュー前のコード品質が安定し、開発プロセス全体の効率化につながっています。
現場からは「初期実装のスピードが上がった」「AI提案をきっかけにチーム内の議論が深まった」といった声が挙がっており、単なる補助にとどまらずコミュニケーションの活性化にも寄与しています。正式な数値は未公表ですが、社内では工数削減や納期短縮といった効果が確認されており、今後はさらに幅広いプロジェクトでの活用が検討されています。大手通信キャリアが実務に組み込んだことで、国内におけるCopilotの信頼性が一層高まっています。
事例4:マクニカ(DX事業)
技術商社として知られるマクニカは、DX推進事業の一環としてGitHub Copilotを導入しました。目的は、コーディング作業やレビュー業務の効率化、そして開発全体のスピードアップです。Copilotを利用することで、日常的に発生するルーチン的なコード記述が大幅に減少し、エンジニアが付加価値の高い業務に集中できるようになりました。
さらに、GitHub Enterprise Cloudへの移行と組み合わせることでCI/CDの自動化も進み、開発から運用までの一連のプロセスが効率化されています。AWS環境とも連携することで、監視やメンテナンス負荷が軽減され、運用チームの負担も軽くなりました。マクニカはこうした実績を顧客向けのDX提案にも活かしており、「自社で得た知見を顧客に展開する」という好循環を生み出しています。自社内の改善と顧客提供価値の向上を同時に実現した点が特徴的です。
まとめ
LINEヤフーによるGitHub Copilotの導入は、単なるツールの活用にとどまりませんでした。小規模テストから始まり、ルール整備や教育を経て全社展開へと進めたプロセスには「AIを安心して使える環境づくり」への強い意志が見て取れます。
導入によって、エンジニアは1日あたり1〜2時間の余裕を得ただけでなく、開発の進め方そのものにも変化が生まれました。AIが提示するコードをきっかけに議論が活発化し、チーム全体のスピードが向上しているのです。さらに、利用を通じて「AIと協働する働き方」が徐々に定着しつつあります。
今後はコード以外の領域への応用や、エンジニア教育への活用も期待されています。LINEヤフーが描く「人とAIが共に開発する未来」は、業界にとって大きな示唆を与えるものです。GitHub Copilotの事例は、他の企業が生成AIを導入する際の指針にもなるでしょう。



返信 (0 )