生成AIを活用した業務改革が加速する中、富士通株式会社は独自の基盤「Fujitsu Kozuchi AI Agent」を軸に、意思決定支援や現場安全管理に革新をもたらしています。本記事では、同社が直面していた課題、導入したAIの具体事例、得られた成果、そして富士通の企業概要までを詳しく解説します。
富士通が直面していた課題とAI導入の必然性
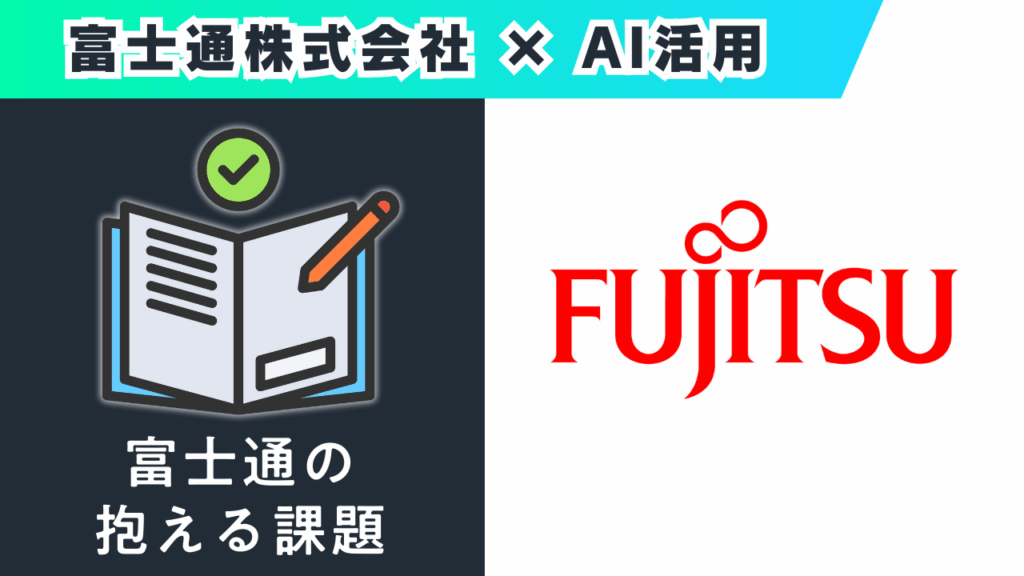
出典:FUJITSU
富士通株式会社は日本を代表するICT企業として、公共から製造、金融まで幅広い領域の顧客を支えてきました。しかしデジタル化の加速に伴い、顧客が抱える課題は複雑化し、既存の業務プロセスだけでは十分に対応できない場面が増えてきました。会議における意思決定は情報の整理不足や分析遅延により迅速さを欠き、現場業務では安全性の確保や効率化において限界が見え始めていました。
こうした背景から、従来の人手中心の運営方法だけでは対応しきれない問題が浮き彫りになり、AIを活用した新たなソリューションの必要性が急速に高まりました。富士通はこの課題を解決するため、生成AIを活用した実用的なエージェント開発に着手し、具体的な導入事例を通じて現場改革を進めています。
会議での意思決定に潜む非効率性
大規模な会議は重要な意思決定の場である一方、参加者の発言内容を裏づけるデータや資料がその場で提示されないことも多く、結論が先送りされる傾向が見られます。富士通においても、膨大な情報を持ち寄る会議で即座に適切な分析を行うのは難しく、結果として生産性が低下する課題がありました。
加えて、資料作成やデータ検証に時間がかかり、会議が終わった後にようやく意思決定に必要な情報が揃うケースも少なくありません。こうした非効率性は、業務全体のスピードを鈍化させる要因となり、競争力の低下につながるリスクを孕んでいました。AI導入の動機のひとつは、この「情報分析の即時性」を実現することにあります。
現場オペレーションの安全性と効率の両立
もうひとつの課題は、製造・物流・建設といった現場における安全管理と効率化の両立でした。従来は人間の監督者が映像や作業手順を目視で確認していましたが、膨大な作業量と長時間労働が限界をもたらし、リスク検出の遅れが事故につながる恐れがありました。
人材不足の進行も加わり、従業員に過度な負担がかかることで現場全体のパフォーマンスが低下する懸念もありました。こうした背景から、AIを活用して安全性を高めると同時に効率性を追求する仕組みが求められたのです。富士通は現場データを活用し、危険をいち早く検出しながら改善提案まで行えるAIの仕組みづくりを進めることで、この難題に取り組み始めました。
Fujitsu Kozuchi AI Agentとは – 戦略的AI基盤の位置づけ

引用:FUJITSU
Fujitsu Kozuchi AI Agentは、富士通が2024年に発表した生成AI戦略の中核を担う仕組みであり、従来の単一モデル活用にとどまらない柔軟な基盤を特徴としています。従来、AIは特定の業務ごとに個別導入され、社内全体で横断的に活用するのが難しいという課題がありました。Kozuchiはその制約を取り払い、複数のAIモデルを統合し、自然言語による操作で利用者が目的に応じて最適な解析や判断を引き出せるよう設計されています。
これにより、専門知識を持たない従業員でも容易にAIを活用でき、意思決定の質や業務効率を高めることが可能になりました。さらに富士通は「AIと人が協働する」という未来像を描き、単なる業務効率化ではなく新しい働き方を提示することを目的としています。
複数モデルを統合する基盤としてのKozuchi
Kozuchiは、個別に機能するAIモデルを束ねることで、業務横断的な活用を可能にした点が大きな特長です。利用者は自然言語で質問を投げかけるだけで、必要な解析やデータ処理を実行でき、裏側では最適なモデルが自動的に選択されて実行されます。従来のように「どのモデルを使うべきか」を利用者が判断する必要がなくなり、導入と運用のハードルが大幅に下がりました。
特定部門での利用に限らず、営業、開発、経営企画など幅広い部門で応用できるため、全社的なデジタルトランスフォーメーションを加速させる役割を果たします。
人とAIの協働を前提とした設計思想
富士通が強調しているのは、AIを万能の自動化ツールとして扱うのではなく、人間と協働する存在として設計することです。Kozuchiは回答や分析結果を提示する一方で、最終的な意思決定は人間に委ねられる構造になっています。これにより誤答や偏りのリスクを軽減しつつ、信頼性の高い業務支援を実現します。
人間の判断力とAIの処理能力を組み合わせることで、両者の強みを最大限に引き出すことが可能となり、従来のAI活用の弱点を補完する仕組みとなっています。この発想は「Trusted AI」という富士通の理念とも合致しており、社会に安心して受け入れられるAIの実現を後押ししています。
富士通が導入したAI事例 – Kozuchiを支える実践例
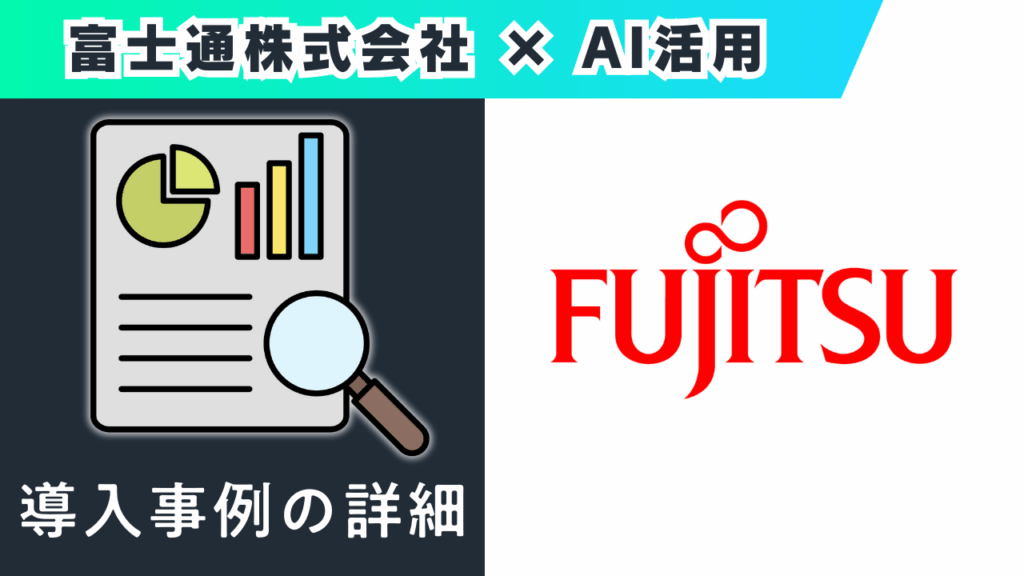
Fujitsu Kozuchi AI Agentは基盤としての役割を担いますが、実際に現場で活用される際には具体的なエージェントの形を取ります。富士通はその一例として「Meeting AI Agent」と「Video Analytics AI Agent」を展開し、意思決定支援や現場安全に直接寄与しています。これらはKozuchiの思想を具体的に体現した事例であり、業務の質を大きく変革しています。
Meeting AI Agent – 会議の質とスピードを変革
Meeting AI Agentは、会議に自律的に参加し、発言内容を解析して関連情報を自動的に提示するエージェントです。例えば「アジア市場の売上が半減した」という発言があれば、直ちに関連する売上データを取り出し、地域別比較を行い、グラフとして可視化します。
従来は会議後に担当者がデータを整理し資料を用意する必要がありましたが、この仕組みによってその場で即座に議論を深めることが可能となりました。結果として、意思決定の迅速化と精度向上が同時に実現され、会議の生産性が飛躍的に向上しています。
Video Analytics AI Agent – 映像解析による現場支援
Video Analytics AI Agentは、現場に設置されたカメラ映像を解析し、安全規定と照合して危険行動を検出するAIです。例えばフォークリフトと作業員の距離が接近した場合、即座に「危険接近」と判断し、報告用のドラフトを作成します。単なる監視ではなく、改善提案まで自動で行える点が特徴です。
従来は人間の監督者が目視で長時間映像を確認する必要がありましたが、AIの導入により24時間体制で監視が可能となり、事故を未然に防ぐ効果が期待されています。結果として現場の安全性が高まり、同時に効率化も進むことで生産性向上につながっています。
導入による効果と今後の展望
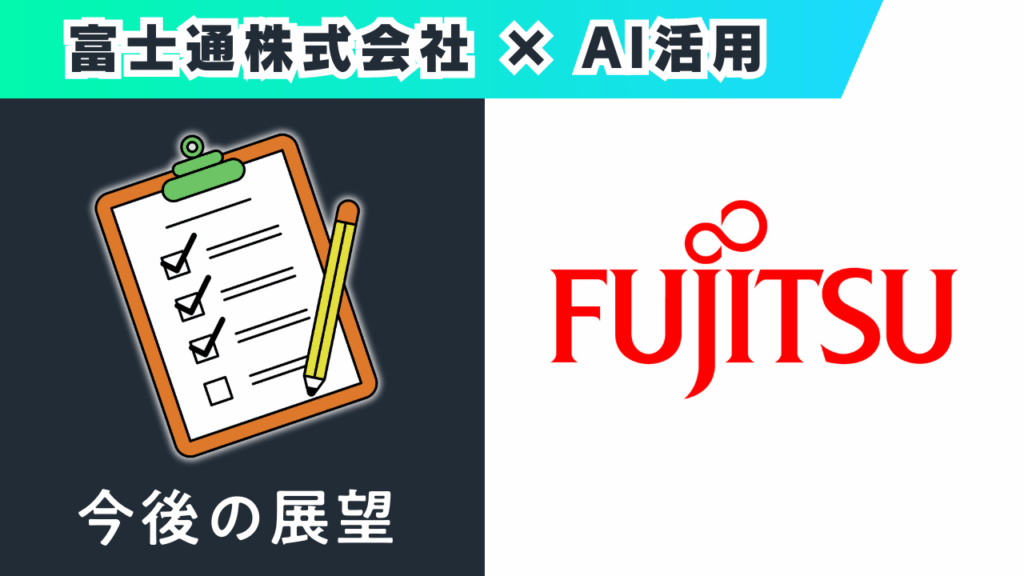
Meeting AI AgentとVideo Analytics AI Agentの導入は、富士通の業務に大きな変革をもたらしました。従業員は単純作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになり、会議ではスピードと精度が向上し、現場では安全性と効率性が両立しました。
業務効率化と付加価値業務へのシフト
AIエージェントの導入により、従業員の役割は大きく変化しました。会議資料の作成や映像監視といった単純作業はAIに任せることで、担当者は高度な判断や戦略立案に集中できるようになっています。これにより、従業員が本来の専門性を発揮できる環境が整備され、企業全体の競争力向上につながっています。
Trusted AIと持続可能な社会への貢献
富士通はAI活用において倫理性や透明性を重視する「Trusted AI」の理念を掲げています。これはAIがブラックボックス的に使われるのではなく、説明可能性や公平性を担保したうえで社会に浸透させるという考え方です。Kozuchi AI Agentはこの理念を実装する具体的な仕組みであり、企業の業務改革を支援すると同時に、持続可能な社会の実現に寄与しています。
富士通株式会社の概要

引用:FUJITSU
ICT企業としての歩みと成長
富士通は1935年に設立され、日本の情報通信技術をリードしてきた歴史を持ちます。ITインフラ、クラウドサービス、ネットワーク、ソフトウェア開発など多岐にわたる事業領域を展開し、国内外で幅広い顧客基盤を持っています。グローバル展開を進めながら、国内市場でも安定した存在感を維持し続けています。
社会課題解決を重視する経営姿勢
同社は「イノベーションによる持続可能な社会の実現」を経営パーパスに掲げています。AIやクラウドを駆使し、社会課題の解決と企業の成長を同時に追求する姿勢は、顧客からの信頼につながっています。Fujitsu Kozuchi AI Agentの展開もその一環であり、業務効率化だけでなく社会全体の豊かさに寄与する取り組みとなっています。
製造業でのAI導入事例

富士通株式会社以外にも、AI技術を導入した企業は数多く存在します。ここでは、AI技術を活用した製造業の事例を紹介します。
ARUMCODE – 熟練技術者の加工プログラムをAIが自動生成
「ARUMCODE」は、熟練技術者が作成する精密加工用プログラムをAIで自動生成するソフトウェアです。例えば、従来16時間を要した加工プログラムの作成をわずか15分で完了させることが可能になりました。
設計図をアップロードし、スタートボタンを押すだけで、複雑な形状にも対応した加工プログラムが出力されるため、技術者の経験に依存した手作業が不要となります。AIが技能と知識を取り込んだ製造AIとして機能し、精密部品の製造現場では劇的に効率化とコスト削減が進んでいます。日本政府の公共サイトでも紹介されており、製造業へのAI導入の有力な成功モデルと言えるでしょう。
東京エレクトロン – AIによる労災防止と現場安全の強化
半導体製造装置の大手、東京エレクトロンは製造現場の安全性確保のため、AIを活用した労災防止システムを導入しました。工場に設置された監視カメラの映像をリアルタイムでAIが解析し、作業員の動きや異常な挙動を検出すると、音や光を通じて即座に注意喚起します。装置の操作に迷う様子を察知して警告する機能もあり、事故の未然防止に効果を発揮しています。
AI処理は現場で完結しクラウドを経由しない方式を採用しており、セキュリティ要件が高い製造業でも安心して導入できる設計です。結果として、安全性の向上と効率的な現場運営が両立されました。
日本触媒 – AIによる生産計画最適化で工数を1/10に削減
化学産業において、日本触媒はAIを活用して生産計画の最適化を実現し、プランニングにかかる工数を従来の10分の1に削減しました。AIが需要予測や注文状況、工程能力などを総合的に分析し、最適なスケジュールを割り出すことで、人的な調整を大幅に減らすことに成功しています。
この成果は生産効率の向上だけでなく、柔軟かつ迅速な対応力の強化にもつながり、製造ラインの強靭化とコスト削減を両立させる先進的な導入事例と言えます。
キリン醸造 – AIによる需要予測で在庫過多と欠品を抑制
キリン醸造では、AIによる需要予測を導入し、在庫過多や欠品といった問題を改善しました。販売データや季節変動、プロモーションなどをAIが解析し、最適な生産・補充計画を策定することで、適正在庫の維持が可能になりました。
この取り組みによって、過剰在庫によるコストと欠品による機会損失を同時に抑制し、効率性と顧客満足の両立を図っています。生産リスクを低減しつつ、販売機会を逃さない仕組みとして注目されています。
まとめ
Fujitsu Kozuchi AI Agentは、AIを人と協働させる基盤として、富士通が直面していた課題を解決するために導入されました。Meeting AI AgentやVideo Analytics AI Agentの実践例を通じて、意思決定の迅速化や現場の安全確保といった具体的成果が示されました。
今後も富士通は「Trusted AI」を軸に、社会に安心して受け入れられるAIの姿を追求し、企業活動と社会課題解決の両面で貢献していくことが期待されています。












返信 (0 )