「ChatGPTに“200字で書いて”とお願いしたのに、実際には180字しかなかった」「逆に長すぎて困った」——そんな経験はありませんか?実は、多くのユーザーが直面しているのが 「ChatGPTは文字数をきっちり守らない」 という問題です。
しかし安心してください。プロンプトの工夫や生成後の調整方法を知れば、ChatGPTに文字数を守らせることは可能です。
本記事では、なぜ文字数を守らないのかという原因から、具体的な改善方法・シーン別の工夫・便利なツールの活用法まで徹底的に解説します。記事を読み終える頃には、あなたも「ChatGPTを文字数指定で自由に操れる」ようになるでしょう。
ChatGPTが文字数を守らないのはなぜか?仕組みを理解しよう

「100字でまとめて」と指示したのに長くなったり短くなったりするのは、多くの人が経験することです。これはChatGPTが意図的に無視しているのではなく、AIの仕組みによる自然な結果です。
ChatGPTは確率的に次の単語を予測しながら文章を生成しており、「意味の自然さ」を優先します。そのため、厳密な文字数よりも、文脈として違和感のない文章を出すことが多いのです。
なぜ「100字ピッタリ」にならないのか?
ChatGPTは言語モデルと呼ばれる仕組みで動いています。これは「次に続く単語はどれがもっとも自然か」を予測して文章をつなげていく仕組みです。
人間が文章を書くときに「この表現の方が伝わりやすい」と直感的に選ぶのと似ています。このため、指示通りの文字数にピッタリ合わせるよりも「文脈として自然にまとまるかどうか」を優先します。
例えば100字と指定しても、98字や110字になることはよくあるケースです。
さらに、日本語と英語での処理の違いや、句読点や改行の扱いによっても誤差が生じやすいのです。
つまり「ChatGPTは文字数を意識できない」のではなく「厳密な制御が得意ではない」ことを理解しておく必要があります。
要約や翻訳で文字数がズレやすい理由
要約や翻訳を依頼すると、指定文字数との差が出やすいのはなぜでしょうか。それは、元の文章の情報量やニュアンスをそのまま伝えようとするからです。
例えば「300字で要約して」と頼んでも、情報を削りすぎると意味が変わるため、AIは安全策として少し長めに出すことがあります。
逆に短すぎる場合も、情報を圧縮しすぎて「これ以上削れない」と判断した結果です。翻訳ではさらに、言語ごとに1文字の情報密度が違うため、英語から日本語にすると文字数が増えてしまいます。
つまり、AIが守らないのではなく、「意味を壊さない範囲での調整」することを優先しているのです。
ChatGPTと文字数指定の相性
ChatGPTはもともと「自然に見えるテキストを生成する」ことに特化しており、「厳密な文字数管理」は得意分野ではありません。
特に日本語では、漢字・ひらがな・カタカナが混ざるため1文字の情報量が揃わず、ピッタリ合わせにくい特徴があります。さらに、AIは「文字数」という概念より「トークン(文章を分割した単位)」で内部処理をしているため、人間が数える文字数とはズレやすいのです。
例えば「今日は晴れです」は日本語では6文字ですが、AI内部では「今日」「は」「晴れ」「です」と複数のトークンに分けて処理されています。この違いも「文字数を守れない」原因のひとつです。
ChatGPTに文字数を守らせるプロンプトの基本

ChatGPTに文字数を守らせたいときは、ただ「100字で」と書くだけでは不十分です。AIは自然さを優先するため、曖昧な指示では守られにくいのです。
そこで効果的なのが「◯◯字以内」「◯◯字程度」といった幅を持たせた表現や、「編集者として100字に収めてください」といった役割指示です。
ここでは、基本となる3つの工夫を紹介します。
「◯◯字以内」と「◯◯字程度」の違いを理解する
「100字で文章を書いて欲しい」場合、あなたはどのようなプロンプトを書くでしょうか?実は「100字以内」と「100字程度」では結果が大きく変わります。
「以内」と書いた場合、AIは100字を超えないように配慮するため、短めに出力されやすくなります。一方で「程度」と指定すると、95〜105字のように近い範囲で調整されやすくなります。
つまり「厳密さ」を求めるなら「以内」、「自然さ」を重視するなら「程度」が有効です。
SEO記事のメタディスクリプションや試験の解答など厳密に制御したい場面では「以内」、ブログ本文やSNSでは「程度」を活用する、と使い分けると効果的です。
役割を与える:編集者や校正者として書かせると精度UP
ChatGPTは「役割を与える」ことで出力が大きく変わります。例えば「あなたはプロの編集者です、120字以内で要約してください。」と指示すれば、AIは「編集者の視点」を想定して文字数に気を配りながら文章を作る傾向があります。
逆にただ「120字で」とだけ伝えると、AIは自然な表現を優先し、指定を軽視しやすいのです。
これは人間に「短めでお願いします」と伝えるより「140字に収めたいからツイート用に調整して」と頼む方が伝わりやすいのと同じです。
プロンプトで役割や目的を明示することが、文字数を守らせる最もシンプルで効果的なコツといえるでしょう。
ChatGPTにセルフカウントさせる裏ワザ
もうひとつ効果的な方法が「AI自身に文字数を数えさせる」やり方です。
例えば「200字以内で要約してください、最後に文字数をカッコ内で表示してください。」と指示すれば、ChatGPTは自分でカウントを行い、結果を明示してくれます。
その後で「190字でした。残り10字追加してください」と修正依頼をすれば、かなり正確に調整できます。
注意点は、AIが数え間違える場合もあるので、最終的には人間がカウンターで確認することです。
この「セルフカウント+再調整」の組み合わせは、メタディスクリプションやSNS投稿など文字数制限がシビアな場面で特に役立ちます。
ChatGPTで文字数をコントロールする実践テクニック

「指定どおりの文字数に近づける」ためには、出力を一発勝負にせず段階的に整えるのがコツです。①まず書かせる→②文字数を数えさせる→③不足や超過ぶんだけ再調整、という再帰的リライトが最も安定します。さらに分割生成や外部カウンターの併用で、誤差を素早く吸収できます。以下で具体手順を紹介します。
生成後に「現在◯◯字、あと△△字で調整」と指示する方法
最初に“最高の一発”を狙うより、書かせてから詰める方が精度が上がります。ワークフロー例は次のとおり。
- まず「120~130字で要約して。最後に[]で文字数を表示」と依頼。
- 返ってきたら自分でも文字数を確認(誤差対策)。
- 超過なら「キーワードは残して冗長表現だけ削減。目標は120字前後」/不足なら「新情報は増やさず要点を補い+10~15字」など差分指示を出す。
- 仕上げに「語尾の連続回避」「読点過多の是正」「禁止語」などの編集ルールを併記。
| プロンプト例 |
|---|
| 「120~130字。最後に[文字数]。もし130字を超えたら冗長語を削る/不足なら要点を1つだけ補う。キーワード:◯◯、△△。新情報追加禁止。文末の重複回避。」 このカウント→差分調整のループを2~3回繰り返せば、過剰な削りや不自然な引き伸ばしを避けつつ、狙いのレンジに収めやすくなります。 |
分割プロンプトで「段階的に作らせる」方法
長文や密度の高い要約は、1ブロックでぴったり収めるのが難しくなります。そこで、構成→各パート→結合の順に分割生成すると、各段で字数を制御しやすくなります。
手順例:
- ステップ1:「全体200字の要約。4要点に分割し、各要点は45~55字。見出し+1文で。」
- ステップ2:「要点1のみ出力。50字前後で。最後に[文字数]。」→調整OKなら要点2へ…
- ステップ3:4要点が揃ったら「4要点を自然につなげた200字前後の1段落に再構成。重複は圧縮。」
- ポイントは各ブロックに予算文字数を割り当てること。途中で超過・不足が出ても、当該ブロックだけを微修正すればよく、全体の崩れを防げます。最後に「結合後の全体文字数を表示して再微調整」という締めを入れると、誤差を小さくできます。
外部ツールとの併用:Word/Googleドキュメント/専用カウンター
ChatGPT内部のカウントは概ね正確ですが、全角・半角・記号・絵文字の扱いでズレることがあります。確実性が要る場面(メタディスクリプション、応募要項、文字数制限のあるフォーム)では、外部カウンターで最終確認しましょう。
使い分けの目安:
- Googleドキュメント/Word:文法・表記ゆれ・語数/文字数の確認を一括で。
- Webの文字数カウンター:全角/半角、改行、句読点の扱いを切替可能なものが便利。
- CMS(WordPress等):プラグインのカウンターで“実際に掲載される文字数”に近い値を把握。
注意点は、スペースや改行をどう数えるかの仕様差。提出要件に合わせ、数え方(文字数/バイト数/マルチバイト扱い)を確認し、同じ方法で最終チェックに統一しましょう。
実践例:200字メタディスクリプションを作る手順
実務でよくある「約200字のメタディスクリプション」を例に、手順を示します。
| ステップ | 特徴 |
|---|---|
| 初稿生成 | 「編集者として、約200字で要約。必須語:◯◯、△△。冗長語禁止。最後に[文字数]。」 |
| 差分調整 | 200字を超過 → 「意味を変えず冗長語を削る。キーワードは維持。190~200字で。」 200字に満たない → 「新情報を増やさず要点を補強。5~10字だけ増やして。」 |
| 仕上げ | 「語尾の連続回避/読点は3つ以内/固有名詞は原文準拠。最終出力後に[文字数]。」 |
| 外部確認 | CMSや専用カウンターで最終チェック。もし差異が出たら「◯字超過なので、意味を変えず2~3語削除」と再依頼。 |
初稿→差分→仕上げ→外部確認の一連で、再現性高く“約200字”に収められます。
文字数を守らせたいシーン別の工夫

「どの場面で、どこまで厳密に合わせるか」を決めると、プロンプト設計が楽になります。メタディスクリプションのように上限が明確な場面は“厳密制御”、レポートやSNSのように幅がある場面は“レンジ制御”が基本です。ここでは、メタディスクリプション/レポート・論文/SNS投稿/SEO記事の見出し・リードの4シーンで使える具体的な工夫を紹介します。
SEOライティングでの活用
検索結果でのクリック率を左右する要素なので、厳密制御が前提です。まず「編集者の役割」を与え、「◯◯字以内」「最後に[文字数]を表示」でセルフカウントさせます。要点は①主要キーワードは冒頭寄せ、②ベネフィットと差別化を1文で、③冗長語・重複表現を禁止、④語尾の連続回避。
| ▼プロンプト例 |
|---|
| 「あなたは編集者です。120~155字でメタディスクリプションを作成。主要KW:『chatgpt 文字数 守らない』を前半に。重複表現禁止、語尾変化、最後に[文字数]。」 |
出力後に外部カウンターで検算し、数字がズレたら「意味を変えずに-5~-10字」など差分リライトを指示します。不要語の削除(「とても」「かなり」等)と係り受けの圧縮で整えると、品質を落とさず規定内に収まります。
レポート・論文での活用
評価基準は「論旨の一貫性」と「根拠の妥当性」。段落ごとに字数予算を割り振ると、全体の字数管理がしやすくなります。プロンプトは①先に章立てを作る、②各段落**○○字程度で要旨→③最後に全体合算**を表示。
| ▼プロンプト例 |
|---|
| 「テーマXを4段落で構成。各段落250~300字で要旨のみ。引用は出典名のみ記載。最後に合計[文字数]。」 本文を書くときは「定義→主張→根拠→反論→小結」の骨格テンプレを固定し、超過時は反論の枚数や具体例の字面で微調整。 |
不足時は因果の接続語や具体例1点の追加で自然に増やします。最後に「引用・注の字数含む/含まない」の規定に合わせて再カウントするのを忘れずにしましょう。
SNS投稿(X/Instagram など)での活用
SNSはプラットフォームごとの上限と視認性が重要。まず目的を「反応(いいね・保存)」か「遷移(クリック)」かで分け、冒頭20~30字のフックを最優先します。
| ▼プロンプト例 |
|---|
| 「X向けに上限文字数内で投稿。冒頭に強いフック、本文は3点列挙。ハッシュタグは3~5個まで、ブランド名1回。最後に[文字数]。」出力後は、プラットフォーム上で改行/絵文字/URLのカウント仕様が差になるため、実画面で再確認。 |
オーバー時はハッシュタグの削減と冗長な副詞の削り、不足時は具体的メリット1語追加で調整します。Instagramの長文キャプションは1行目で結論→改行→箇条書きが有効です。
保存目的ならチェックリスト型の体裁にすると、字数を守りつつ読了率が上がります。
SEO記事の見出し・リード文での活用
見出しは検索意図×主要KWを含めつつ、表示幅に収まるようレンジ指定。「32~40字」など幅のあるガイドが実践的です。
| ▼プロンプト例 |
|---|
| 「H2見出しを32~40字で3案。主要KWは左寄せ、重複語回避、ユーザーの悩みを具体化。各案の[文字数]。」 リード文は読者の状況→問題→解決→読む価値の順で180~260字程度に。 |
最後に「本文の約束(何が得られるか)」を1文で締めるとクリック後の直帰率改善に効きます。オーバー時は形容詞と序文を削り、不足時は成果物の具体像(例:テンプレ、手順、チェックリスト)を1フレーズだけ追加。
語尾の多様化も読みやすさと字数調整に役立ちます。
ChatGPTは文字数より内容を優先する?心構えを持とう

ChatGPTが文字数を守らないと感じるのは、AIが「正確な制御」より「自然で意味のある文章」を優先しているからです。
つまり、誤作動ではなく性質上の問題です。大切なのは「AIを完全にコントロールする」のではなく「ある程度の誤差を前提に付き合う」こと。
文字数はあくまで目安、最終的な調整は人間が行う、という心構えが欠かせません。
AIに完全依存しないことが大切
AIは非常に便利ですが、「AIが出したものをそのまま使えばいい」と考えると依存が強まり、期待通りの成果が出ないことが多いです。
特に文字数制限がある課題では、ChatGPTに一発で任せても誤差が出やすく、思った通りに仕上がらないことも珍しくありません。
そのため、AIは下書きや補助にとどめる姿勢が大切です。出力を受け取ったら必ず自分でチェックし、必要に応じて編集や削減を加えましょう。
AIを「便利な計算機」ではなく「頼れるアシスタント」と位置づけ、自分自身が最終責任者として調整を加えることが、健全に活用する最大のコツです。
文字数と情報量のバランス
文章は「長ければ良い」「短ければ良い」わけではなく、情報量とのバランスが重要です。
ChatGPTが文字数をオーバーするのは、情報を削りすぎると意味が伝わらなくなると判断した結果でもあります。
逆に短すぎる場合は、冗長さを避けようとした結果かもしれません。
つまり、AIは「情報を守る」ことを優先しており、文字数指定は二の次になりがちなのです。
利用者側も「目的に必要な情報がきちんと入っているか」を重視しつつ、文字数は後から整えるくらいの心構えを持つと安心です。
まずは情報量をチェック、そのうえで文字数に合わせるのが実用的な流れです。
最終調整は人間が行うべき理由
ChatGPTは「ほぼ正確」に文字数を合わせられますが、100%厳密に制御するのは難しいです。さらに、文字数を無理に守らせようとすると、表現が不自然になったり、読みづらくなるリスクがあります。
そのため、最終調整は必ず人間が行うべきです。例えばSEO記事のメタディスクリプションなら、AIに作らせた後に手作業で数文字削るだけで十分なケースが多いです。
逆に不足している場合は、具体例や接続語を少し加えると自然に伸ばせます。要は「AIに9割仕事をさせ、最後の1割を自分で整える」イメージです。このワークフローを徹底すれば、精度も品質も高めながら、AI依存を避けることができます。
ケーススタディ:文字数指定で失敗した例と成功した例

理論だけではイメージが湧きにくいため、実際の利用場面を例に挙げます。ここでは、大学生が課題で指定字数に収められなかった事例、SEO記事でリード文が短すぎた事例、SNSで投稿がオーバーした事例を紹介。
それぞれの失敗原因と改善策を解説し、最後に「成功プロンプト」を示すことで、実務にそのまま活かせる具体例をお伝えします。
100字の自己紹介が120字になったケース
ある大学生は「就活用に100字の自己紹介を作ってほしい」とChatGPTに依頼しました。しかし出力は120字を超え、エントリーシートの文字数制限に収まりませんでした。
原因は「100字で」という指示だけで、目的や重要キーワードを指定していなかったことです。
改善策としては「100字以内」「自己PR」「キーワードは責任感と協調性」と具体的に依頼すること。さらに「最後に文字数を表示」と加えると確認も容易です。この修正後、AIは96字で的確な自己紹介を生成できました。
文字数指定においては、数字だけでなく「用途」「必須ワード」「制約条件」を与えることが成功の鍵となります。
SEO記事のリード文が短すぎたケース
あるライターは「300字のリード文」を依頼しましたが、出力はわずか180字しかなく、内容が薄くなってしまいました。原因は「300字で」という指示だけで、具体的な情報量の期待値を伝えなかったことです。
AIは「短めにまとめる」ことを優先しすぎたため、結果として不足が生じました。改善方法は「300字程度で、読者の悩み→解決策→記事を読むメリットの順に盛り込む」と構造を明示することです。さらに「不足していたら追加して」と繰り返し修正を依頼すれば、最終的に298字でバランスの取れたリード文が完成しました。指定字数を守らせるには「文字数」+「構成」まで含めたプロンプトが必要です。
SNS投稿でオーバーしてしまったケース
SNS担当者が「140字でツイート用の文章を」と依頼したところ、結果は155字でオーバー。原因はハッシュタグや絵文字を多く盛り込みすぎ、ChatGPTがそれを優先したことです。改善策としては「140字以内。ハッシュタグは最大2つ。絵文字は1つまで」と制約条件を明記すること。
また「最後に文字数を表示」と加えれば、調整の際にどこを削るか判断しやすくなります。修正後、AIは138字で収めることができ、実際の投稿でも違和感なく使用できました。SNSでは「強調表現や装飾を減らす」「情報量を削る」の2ステップで効率的に調整するのが有効です。
成功例:文字数を守れたプロンプトと工夫
これらの失敗から導かれる共通点は「文字数指定だけでは不十分」ということです。成功したケースでは、以下の工夫がポイントでした。
- 幅を持たせる:「100字ピッタリ」ではなく「95~105字」などレンジ指定。
- 役割を与える:「編集者として」「就活エントリー用に」など文脈を設定。
- セルフカウントを促す:「最後に[文字数]を表示」と指示。
- 差分調整を繰り返す:「5字削って」「10字足して」と段階的に調整。
実際にこの手法を使うと、200字メタディスクリプションや300字リード文でも高い精度で収まることが確認されています。つまり「数字+条件+チェック」の三段構えが成功の秘訣なのです。
ChatGPTと文字数指定に関するよくある質問(FAQ)

「100字で」と頼んだのにオーバーする/短すぎる、という悩みは多くの人が抱えています。ここでは、なぜ守れないのかという仕組み面から、ぴったり合わせるコツ、数え方の落とし穴、言語差やツール併用の勘所までをQ&Aで整理。実務で迷いがちなポイントを、一問一答で素早く解決できるようにしました。
Q1:なぜ指定文字数を守れないのですか?
ChatGPTは「次に自然な語を予測する」仕組みのため、厳密な文字数より意味の自然さを優先します。内部は“文字”ではなくトークン単位で処理しており、人間の文字数カウントとズレやすいのも理由です。さらに要約や翻訳では、情報の毀損を避けるために安全側(やや長め/短め)に寄ることがあります。
Q2:ぴったり100字にすることは可能?
理論上は近づけられますが、一発で100.0字は安定しません。現実解は「95〜105字のレンジ指定」「セルフカウント(最後に[文字数]表示)」「差分リライト(±5字など)」の三点セット。2〜3回の微調整で限りなく近づけるのが実務的です。**“ピタリ病”**は品質を落とすので避けましょう。
Q3:「◯◯字以内」と「◯◯字程度」どちらが守られやすい?
厳密さ重視なら「◯◯字以内」、自然さ重視なら「◯◯字程度」。前者は短めに収まりやすく、後者は指定近傍に寄りやすい傾向です。実務では、応募要項やメタディスクリプションなど制限が明確な場面は「以内」。ブログやSNSは幅のある程度が扱いやすく、読みにも自然さが出ます。
Q4:どう指示すれば精度が上がりますか?
役割付与(編集者/校正者として)+目的(就活ES/SEOメタ)+制約(禁止語・保持キーワード)+セルフカウントの4点をセットで。例:「編集者として120〜155字で。KWは前半。冗長語禁止。最後に[文字数]。」さらに差分指示(“−10字だけ削る”)で再現性が跳ね上がります。
Q5:数え方の違いでズレます。何を確認すべき?
全角/半角/スペース/改行/絵文字の扱いが要件と一致しているかを必ず確認。提出先の仕様(CMSや応募フォーム)がどこまでを文字数に含むかを先に決め、同じ方法で最終カウントしましょう。外部カウンターやWord/Googleドキュメントで検算し、ChatGPTの[文字数]と突合するのが安全です。
Q6:英語と日本語で守りやすさは違いますか?
違います。英語はスペースや短い単語が多く、字面の微調整が比較的しやすい。一方、日本語は漢字・仮名の情報密度が高いため、1語の削除で想定以上に字数が動くことがあります。日本語では接続詞や冗長表現の整理、重複語の圧縮が微調整の要。レンジ指定との併用が吉です。
Q7:要約や翻訳で指定がズレやすいのはなぜ?
要約は情報の保持と圧縮率のせめぎ合い、翻訳は言語間の情報密度の違いが原因です。AIは意味を壊さないように安全側へ寄るため、指定よりやや長め/短めに出す傾向が出ます。対策は、必須要点を箇条書きで先に与える、出して良い情報量を明示、差分で微調整の三段構えです。
Q8:外部ツールは何を使えばいい?
Word/Googleドキュメントは文法・用字と文字数を同時にチェックできる定番。Web文字数カウンターは全角・半角や改行の扱いを切替できるものが便利。CMSプラグインは“表示上の字数”に近い値を把握できます。最終は提出先の数え方で検算し、ChatGPTの[文字数]と差異があれば差分リライトで詰めましょう。
Q9:生成中に途中で切れてしまいます
最大トークンやストップ条件が原因のことがあります。長文が必要なら「章立て→各章→結合」の分割生成にし、各ブロックに字数予算を割り当てると安定。最後に「全文を◯◯字程度に統合。重複は圧縮。最後に[文字数]」と指示し、1回で終わらせようとしないのがコツです。
Q10:最終的に文字数と品質、どちらを優先すべき?
要件があるなら文字数優先、ただし伝わる品質を犠牲にしすぎないバランスが重要です。まずは情報の過不足を整え、次に言い換え/圧縮で規定内へ。目安は「AIで9割→人が1割の最終調整」。ピタリ合わせを目的化せず、読者にとって意味が通る最短距離を保つのが最良解です。
まとめ:ChatGPTと文字数指定の上手な付き合い方
ChatGPTが文字数を守らないのは「無視している」からではなく、自然で意味の通じる文章を優先する仕組みだからです。完全な制御は難しいですが、プロンプトの工夫やセルフカウント、差分リライトを組み合わせれば高精度に調整できます。
大切なのは「AIは補助、最終調整は人間」という姿勢。AIの特性を理解し、うまく付き合うことで、文字数指定を実務に活かせます。


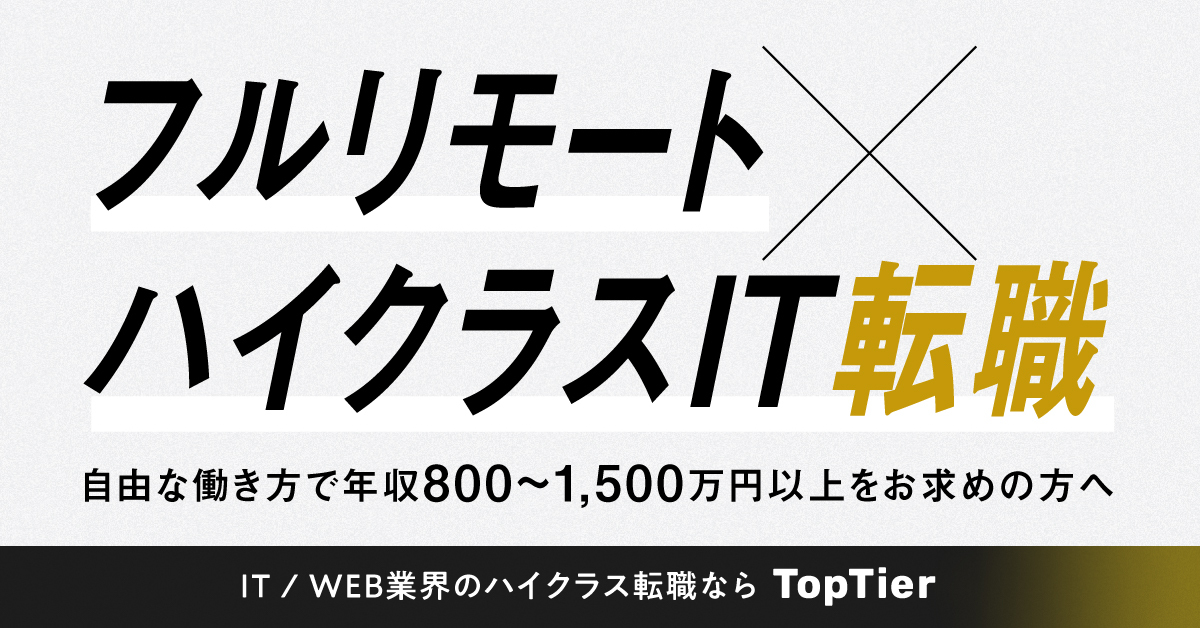
コメント