AIに関連する資格は数多くありますが、その中でも注目を集めているのが「生成AIパスポート」と「G検定」です。
どちらもAIに関する知識を証明できる資格ですが、学習内容、難易度は大きく異なります。そのため「どっちを受けるべき?」「自分にはどちらが合っているのか」と迷う人も少なくありません。
本記事では両資格の特徴を比較し、それぞれの違いや活用シーンを整理することで、自分に最適な資格選びのヒントを提供します。
生成AIパスポートとG検定の概要
| 項目 | 生成AIパスポート | G検定 |
|---|---|---|
| 難易度 | 初級レベル。基礎知識中心で合格しやすい | 中級〜上級レベル。理論的理解が必須 |
| 合格率 | 非公式だが70〜80%程度と高め | おおむね60〜70%程度 |
| 学習時間 | 初心者で30〜40時間、経験者は15〜20時間程度 | 平均100時間以上必要。数学・統計の基礎も推奨 |
| 対象層 | 学生、社会人、AI初心者、リスキリング層 | AIエンジニア、研究者志望、理系人材 |
| 活かし方 | 社内AI推進、就職・転職でのリテラシー証明、教育現場 | AI開発・研究、専門職キャリアの証明 |
| 学習内容 | AI基礎概念、生成AIの仕組み、安全利用・リスク管理 | ディープラーニング理論、機械学習、ニューラルネットワーク |
まずは両資格がどのような位置づけを持っているのかを確認しましょう。生成AIパスポートはAIを安全かつ効果的に使うための基礎資格であり、G検定はディープラーニングを中心にした理論知識を問う資格です。
同じAI関連資格でも目的が異なるため、選ぶ際には自分のキャリアプランや活用目的を意識する必要があります。ここでは両者の概要を整理して紹介します。
生成AIパスポートとは?AIリテラシー基盤を学べる新資格

生成AIパスポートは、AIを活用する際に必要なリテラシーを体系的に学べる資格です。試験内容はAIの基本概念、生成AIの仕組み、著作権や情報漏洩リスクなどの安全利用に関する項目まで幅広く網羅しています。
初心者でも取り組みやすく、社会人のリスキリングや学生の就職活動に役立つ点が特徴です。「AIをどう正しく使うか」に焦点を当てた資格であり、研究者や開発者だけでなく幅広い人材が対象になっています。短期間の学習で合格可能なため、AI学習の最初の一歩としても最適です。
G検定とは?ディープラーニング理論に特化した検定
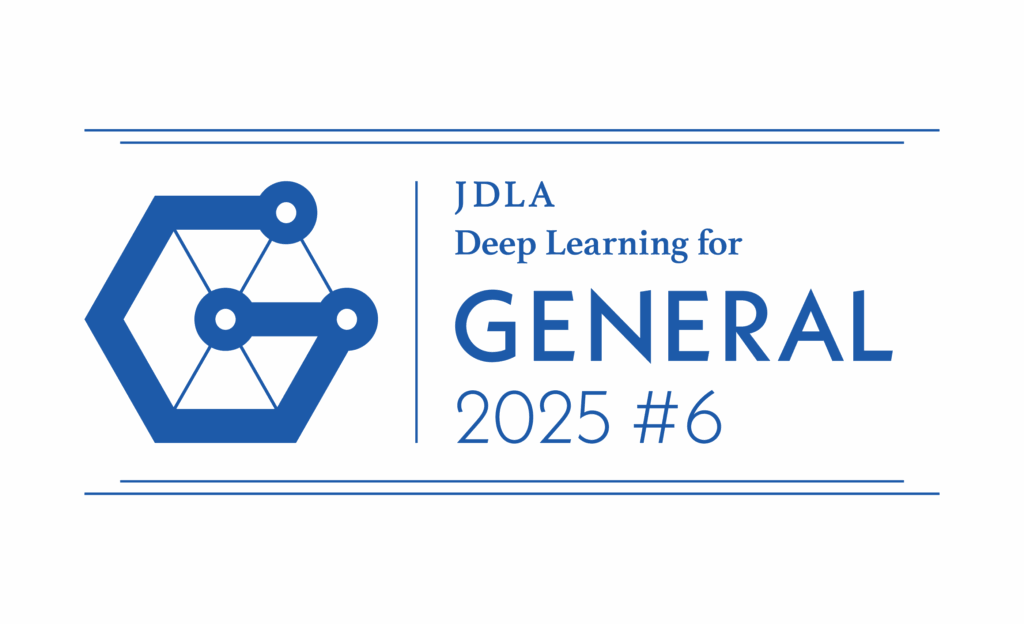
G検定(ジェネラリスト検定)は、日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催する資格で、AIの理論や仕組みに重点を置いています。特にディープラーニングやニューラルネットワークに関する理解が求められ、受験者は数理的な知識も一定レベル必要です。
AIの研究開発やエンジニアリングに関心がある人にとっては必須級の資格であり、専門性の高さが評価されます。「AIをどう動かすか」に焦点を当てた検定といえ、理論や仕組みを深く学びたい層に適しています。
受験者層と目的の違いを整理
両資格はAIに関する知識を扱う点では共通していますが、対象とする受験者像は明確に異なります。生成AIパスポートは学生や社会人など、AIを使う立場の人が基礎を固めるのに適しており、リスキリングや就職活動のアピールに活かしやすい資格です。
一方、G検定はエンジニアや研究者志望の人が、理論的知識を証明するために受験するケースが多く、開発や専門職での評価に直結します。つまり、「AIを使う人向け」と「AIを作る人向け」という大きな目的の違いがあるのです。
難易度・合格率・学習時間の比較

資格を選ぶ際に気になるのが「どのくらいの難易度か」「学習にどれだけ時間が必要か」という点です。生成AIパスポートとG検定はどちらもAI分野に関する資格ですが、合格基準や学習負担には大きな差があります。
ここでは、合格率や必要な勉強時間を比較し、それぞれの試験の挑戦しやすさを明らかにします。
生成AIパスポートの合格基準と学習目安時間
生成AIパスポートは正答率70%前後で合格できるとされ、学習時間の目安は初心者で30〜40時間、IT知識のある人なら15〜20時間程度です。合格基準は決して高くなく、短期間の準備でも到達できる点が特徴です。
難問に答える必要はなく、AIの基本概念やリスク管理、社会的活用などの理解を広く押さえていれば十分合格圏内に入ります。そのため、「短期間でAIリテラシーを証明したい」層に最適な資格といえるでしょう。学習負担が軽く、初めてAI関連資格に挑戦する人でも安心して受験できます。
G検定の合格率・必要学習量の実態
G検定は出題範囲が広く、ディープラーニングや統計、数理的な知識まで問われるため難易度は高めです。合格率は回によって異なりますが、おおむね60〜70%前後と報告されています。
ただし、合格者は相応の準備をしているケースが多く、学習時間は100時間以上を見込む人も珍しくありません。専門用語や理論の理解が必要なため、未経験者が短期間で合格するのは難しいといえます。「AIの理論を本格的に学びたい人向け」の試験であり、キャリア形成の強い意欲がある人が挑戦するケースが目立ちます。
難易度の差から見える「挑戦しやすさ」
両資格を比べると、生成AIパスポートは学習負担が軽く挑戦しやすいのに対し、G検定は理論的な理解を求められるためハードルが高めです。初心者やAIに触れたことがない人にとっては生成AIパスポートが入門に適しており、AIエンジニアや研究志望者にはG検定の方がキャリアに直結しやすいと言えます。
つまり、「短期間で広くAIを理解したい人」には生成AIパスポート、「時間をかけて専門性を高めたい人」にはG検定が向いています。難易度の差を理解することで、自分に合った挑戦先を選びやすくなるでしょう。
学習内容・出題範囲の違い
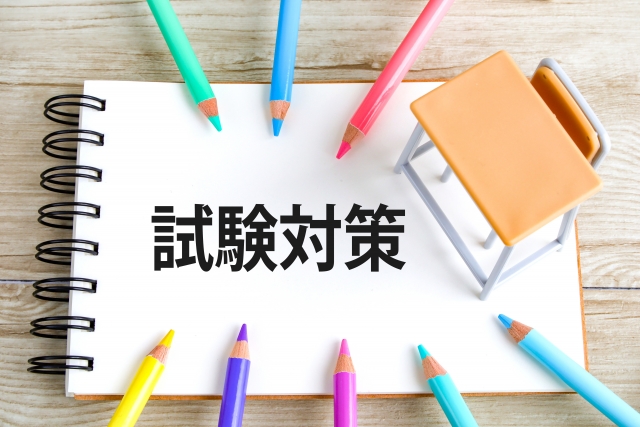
生成AIパスポートとG検定は同じAI関連資格ですが、出題範囲や重視される知識は大きく異なります。前者は幅広い人がAIを安全に使えるようになることを目的としているのに対し、後者は理論や仕組みを理解する専門知識を重視しているのです。
ここでは、それぞれの学習内容を具体的に比較し、両資格が持つ役割の違いを整理します。
生成AIパスポートは実用リテラシー重視
生成AIパスポートの学習内容は、AIの基本概念、生成AIの仕組み、著作権や個人情報保護、情報漏洩リスクへの対応など、実務で役立つリテラシーに重点が置かれています。
出題形式も専門的な数式やプログラミング問題はなく、初心者でも理解できるレベルに調整されています。つまり、この資格を通じて学べるのは「AIをどのように安全かつ効果的に活用するか」という実用的な視点です。
幅広い層がAI活用を安心して始められるように設計された基盤資格であり、社会人や学生にとって実務直結の知識を得られるのが特徴です。
G検定は理論・研究寄りの知識が中心
G検定では、ディープラーニングの仕組み、機械学習のアルゴリズム、ニューラルネットワークの構造、数理的背景など、専門的で理論的な知識が問われます。数学や統計の基礎理解が必要になるため、学習のハードルは高めです。
これらの内容は実務でAIを「使う」よりも、AIを「設計・開発する」際に必要な知識に近いものです。そのため、AIエンジニアや研究者を目指す人にとってはキャリア形成に直結する資格となります。理論的理解を深めたい層には大きな価値を持ちますが、初心者には難しく感じられる部分も多いでしょう。
どちらが自分のキャリアに役立つか
両資格の出題範囲を比較すると、生成AIパスポートは「広く浅く実用的」、G検定は「狭く深く理論的」と表現できます。キャリアに直結させたいなら、自分がAIを「使う立場」か「作る立場」かを見極めることが重要です。
ビジネスでAIを活用したい人や教育現場でAIリテラシーを伝えたい人には生成AIパスポートが適しており、AI研究や開発の専門職を目指す人にはG検定が有効です。つまり、どちらが役立つかは一概には言えず、自分のキャリアゴールに合わせて選ぶことが最適解といえます。
キャリアへの活かし方の比較

資格を取得する目的は、学んだ知識をキャリアに活かすことにあります。生成AIパスポートとG検定はどちらもAI関連の資格ですが、評価されやすい場面や活かし方は大きく異なります。
ここでは、それぞれがどのようなキャリア価値を持つのかを整理し、資格取得後の具体的な活用イメージを解説します。
生成AIパスポートが役立つ場面(実務・社内評価・教育)
生成AIパスポートは、AIを活用するビジネスパーソンや教育現場に立つ人にとって強力な武器となります。社内でAI導入が進む中、「基礎から安全にAIを扱える人材」として信頼を得られ、AIプロジェクトの推進役に抜擢されやすくなります。
また、教育や研修の場では「体系的に学んだ知識を持つ講師」としての立場を築くことも可能です。AIを安全に活用する力を証明できる資格であるため、専門職以外の幅広いキャリアシーンで活かせる点が大きな価値です。
G検定が評価される場面(研究・開発・専門職)
G検定は、AIエンジニアや研究者といった専門職を目指す人にとってキャリア形成に直結する資格です。理論や仕組みを理解していることを証明できるため、AI開発プロジェクトや研究機関、データサイエンティスト職などで高く評価されます。
特に、AI技術を実装する場面ではG検定の知識がそのまま役立つため、専門性の証明として有効です。「理論を理解し開発に活かせる人材」であることを示せる資格として、企業や研究機関からの評価を得やすい点が特徴です。
両方取得することで広がる可能性
生成AIパスポートとG検定は、受験対象や内容が異なるため競合する資格ではなく、むしろ補完関係にあります。両方を取得すれば「AIを安全に使うリテラシー」と「理論を理解して開発に活かす力」の両方を証明でき、キャリアの幅が大きく広がります。
例えば、ビジネス部門と技術部門の橋渡し役を担える人材として評価される可能性が高まるでしょう。複数資格を掛け合わせることで専門性と実用性を兼ね備えた人材になれる点が、両方を学ぶ最大のメリットです。
どっちを取るべき?タイプ別おすすめ資格
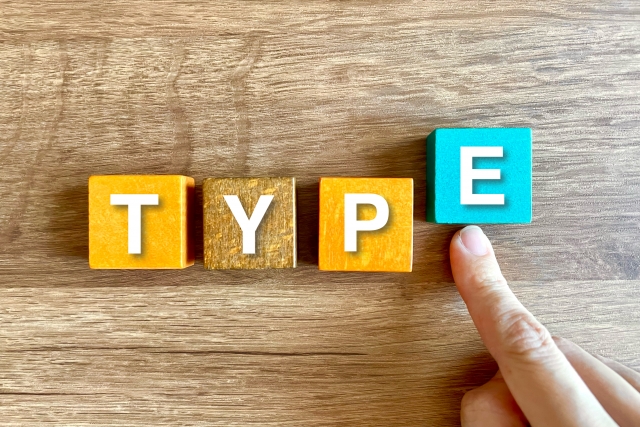
生成AIパスポートとG検定は、それぞれ目的や受験者層が異なるため「どちらを取るべきか」は一概に言えません。大切なのは、自分のキャリアの方向性や学習目的に応じて選択することです。
ここでは、代表的なタイプ別にどちらが適しているかを整理し、自分に合った資格選びの参考になるよう解説します。
初心者・文系人材・学生には生成AIパスポート
AIに触れたことがない初心者や文系出身の社会人、就職活動中の学生にとっては、生成AIパスポートが最も取り組みやすい資格です。専門的な数式や理論の理解は不要で、必要な勉強時間も30〜40時間と比較的短期間で済みます。
そのため「AIを安全に活用できる」というリテラシーを身につけながら、履歴書や職務経歴書に書ける実績を得られるのが魅力です。「まずAIを学んでみたい」「基礎から安心して学びたい」層に最適な入門資格であり、キャリアの最初のステップとして有効です。
エンジニア志望・研究者志望にはG検定
理系バックグラウンドを持ち、AI開発や研究に携わりたいと考えている人にはG検定が適しています。出題範囲はディープラーニングや機械学習の理論にまで及ぶため、学習負担は大きいですが、合格すれば専門性を証明可能です。
企業や研究機関では「理論を理解して開発に活かせる人材」として評価されやすく、専門職志望者には大きな武器になります。「AIを動かす側に立ちたい人」「研究や開発に直結する力を証明したい人」にはG検定が最適です。
両方取得することでキャリアの厚みを増せる
どちらか一方を選ぶのではなく、両方を組み合わせて取得するのも効果的です。生成AIパスポートでAIを安全に活用する基盤知識を身につけ、G検定で理論的な理解を深めることで、実務と専門の両面に対応できる人材になれます。
特に、ビジネス部門と技術部門の橋渡し役を担いたい人には有効で、社内外での評価を高められるでしょう。「AIを使う力」と「AIを作る力」の両方を兼ね備えることで、キャリアの選択肢を大きく広げられるのが両資格を取る最大のメリットです。
まとめ|生成AIパスポートとG検定は補完関係にある
生成AIパスポートとG検定は、どちらが優れているかを競う資格ではなく、対象や目的が異なる補完的な存在です。前者はAIを安全に「使う」ためのリテラシーを証明する資格であり、後者はAIを「作る」ための理論的理解を示す資格です。
初心者やビジネスパーソンには生成AIパスポート、専門職志望者にはG検定が適していますが、両方を取得すれば「実用性」と「専門性」を兼ね備えた強力な人材としてキャリアを広げられます。
自分の目的に合った資格を選びつつ、必要に応じて両方に挑戦することが理想的な戦略といえるでしょう。
| 生成AIパスポートの関連記事 | |
|---|---|
| 取得するメリット | 勉強方法(勉強時間) |
| 合格ライン(合格点) | 意味ないって本当? |
| G検定との違い | |






返信 (0 )